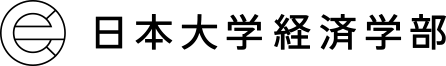佳作 個人部門(学部生) 名倉 実咲
相続税回避目的の不動産にまつわる事例研究
本論文は最高裁令和4年4月19日判決と国税不服審判所による令和5年6月13日裁決の判例研究を行っている。
最高裁令和4年4月19日判決,いわゆるタワーマンション節税は,相続開始前に自己資金や金融機関からの借入を原資としてタワーマンションを購入し,相続税の節税を行うスキームについて,納税者と国税当局が争い,最高裁判決によって納税者側の敗訴となった裁判である。本判例において納税者側の敗訴が揺らがなかった理由の一つに相続税回避の目的が露骨であったからだと推察する。
一方で,国税不服審判所令和5年6月13日裁決は,親が子に対し駐車場である土地の使用賃借を設定し,駐車場の賃料収入を子に帰属させた場合に,その賃料につき対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとして,子に対する贈与税課税が認められた事例である。本件も相続税回避の意図があった事実は認められているものの,大阪高裁および審判所が判断するにあたって補強材料の一つという位置付けであったと推測する。
両者の事例から,相続税回避の意図が露骨な節税は,国税局等から疑われ更正処分等が下る可能性が高いといえる。たしかに不動産の課税価格は,一般的な資産に比べ巨額であるため,わずかでも相続税の課税価格を減らそうと,上記のような大胆な節税に手を出してしまうのであろう。しかし,視野狭窄で節税に手を出した結果,追徴課税や裁判費用の請求がされているようでは,相続税回避はリスクに見合ってない印象を受ける。
本判例研究より,筆者が被相続人となる可能性がある1~3年前に対策を始めるのではなく,日頃から担当税理士と協力しながら適切に相続税対策を行っていく必要があり,過度な節税は踏みとどまるべきであると教訓となった。
また,「死」という突発的な事象に向けた対策は難しいため,日常的な資産運用や自己資産の情報共有が最も重要であると考える。また,相続や会計等知識を蓄えておくことが良識的な判断をする手助けになると思われる。最後に,国民は今一度,財産・権力・地位を持つ者はそれ相応の社会的責任や義務を負う,noblesse obligeの精神を肝に銘じる必要があると強く主張したい。